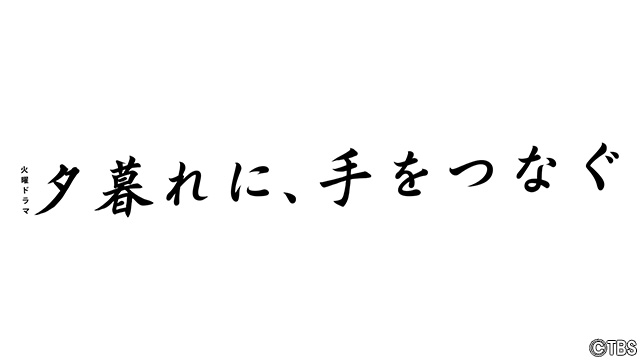浅葱空豆(広瀬すず)にとって、海野音(永瀬廉)は“安定剤”だった。
どんな悲しみも、音の声を聞けばやわらいだ。音がそばにいてくれるだけで、安心できた。だからこそ、音がいないだけで、空豆はたちまちに弱くなってしまう。
『夕暮れに、手をつなぐ』(TBS系、毎週火曜22:00~)第8話は、つないだはずの空豆と音の手が離れる回となった。
広瀬すずは、絶望を知るほど美しくなる
久遠徹(遠藤憲一)が空豆のアイデアを盗作した。それは、空豆のデザイナーとしての尊厳も、1人の女性としての想いも傷つける行為だった。なぜなら、あの「Don’t remember days, remember moments」は、音との思い出そのものだから。
空き缶をゴミ箱に投げっこしたこと。お手玉をぶつけ合ってはしゃいだこと。きらきらと光るシャボン玉。デザインひとつひとつに、音との瞬間がつまっている。他の誰も、2人の思い出に踏み入ることなんできない。それを、むげにされたことが許せなかった。自分の名前以外で、音との思い出が世に出るなんて考えられなかった。
暗い川底に突き落とされた空豆が手を伸ばしたのは、音だった。無機質なコール音すらもどかしそうに、空豆の指が何度も音の電話番号をプッシュする。だけど、音は出ない。いちばんそばにいてほしい人が、いちばんそばにいてほしいときに、いない。
塔子(松雪泰子)からのメールが来たときもそうだ。自分を捨てたはずの母からの優しい激励。整理できない気持ちを吐き出したいのに、いちばんに聞いてほしい音はもう明日にはいなくなる。階段の下で音の部屋を見上げ涙を浮かべた空豆は、置き去りにされた子どもみたいだった。
この第8話は、広瀬すずの俳優としての圧倒的なポテンシャルを堪能できた回でもあった。
母がかつて「なのはな」と書いた掌を見つめたあと、虚空に視線を彷徨わせ、救いを求めるように部屋の外に目をやる。それまで横顔だった表情が、そのとき初めて正面になる。すると、今まで見えなかった右目側の目尻に涙が溜まっているのがわかる。それが、見えなかった空豆の気持ちがさらけ出されたみたいで、はっと胸を衝かれるのだ。
雪の中、音を求めてレコード会社にやってくるところも、あのパワフルな空豆と同一人物だと思えないくらい生命力が消え果てている。磯部真紀子(松本若菜)に音とセイラ(田辺桃子)を呼ぼうかと聞かれ、怯むように首を横に振る。会いたい。でも、こんな自分を見られたくない。心に受けた傷が、全身に浮き出てきたような顔をしている。
音とセイラが抱き合っているのを見て走り去る姿なんて、なんだかこちらまで呼吸が浅くなりそうだ。なのに、とても美しい。淡い雪が舞い散る中、街灯に照らされ、泣き崩れる広瀬すずが、見ていて苦しいのに、その泣き顔まで網膜に焼きつけておきたくなるほど美しい。
いい俳優は、どんな瞬間もフォトジェニックに変えてしまう。広瀬すずのすさまじい吸引力を見せつけられ、しばし呆然となるようなクライマックスだった。
恋を育むのは日々だけど、実らせるのは瞬間なのだ
一方、そんな空豆の絶望を音はまだ知らない。
あの抱擁は、セイラの意地悪だろう。セイラは空豆が好きなのだ。空豆から電話が来た瞬間の「もしもし」が、隠しきれないセイラの気持ちを全部語っている。だけど、空豆はセイラなんてそこにいないように音のことばかり聞く。あのとき、知ってしまった、空豆が見ているのは音だけなんだと。だから、セイラはわざと空豆から音を奪うようなことをして、空豆を自分のもとにとどめたかった。
あのスタジオで音とセイラがどんな話をしていたのかはわからない。でも、音の気持ちそのものは空豆にあるとしか思えない。
雪平響子(夏木マリ)の目隠しを空豆だと勘違いしたときのあの硬直っぷりは絵に描いたみたいにチャーミングで、「たとえば、どんな……?」は吹き出したくなるくらいコミカルで、「ちゃんと空豆に伝えてあげて」と言われて覚悟を決めた真剣な眼差しは揺らぎないほど力強い。
お互いの気持ちはちゃんと向き合っているのに、でもほんの少しずつタイミングがズレるだけで、簡単に距離ができてしまう。だから、恋は難しい。恋を育むのは日々だけど、実らせるのは瞬間なのだ。わずか一瞬のタイミングを逃すと、想いは一生届かない。次回予告で音は「俺、お前のことが好きだった」と告白していた。やっと伝えた気持ちは、過去形。空豆と音の気持ちはこのまま離れ離れになってしまうのだろうか。
できればそんなことないと信じたい。それくらい、2人が積み重ねてきたこれまでの瞬間はどれも美しいものだったから。音を送り出すときの垂れ幕も、音に出ていってほしくない空豆の気持ちを僕たちはよく知っているから、はしゃげばはしゃぐほど胸が痛い。
空豆はオレンジジュースのプルリングを開けた瞬間、音と空き缶を投げっこしたことを思い出した。2階から音を見送るその構図で、ホテルで音の名前を尋ねたときのことを思い出した。そんなふうにたくさんの瞬間が記憶に刻み込まれている。
音もまたデジャヴのように、似たような瞬間が訪れたときに空豆を思い出すのだろう。音という名前を褒められたとき、夕暮れの歩道橋を渡るとき、打ち上げ花火が上がるのをどこか遠くで見上げたとき、きっと音は空豆を思い出す。
そんなふうにずっと記憶に住み続ける人は多くない。そして、そんな人のことを簡単に過去形になんかできない。
すれ違い続けたいくつものタイミングを乗り越えて、まるで時計の長針と短針が重なり合うように、空豆と音の気持ちが通じる瞬間が来ることを、心の底から信じている。