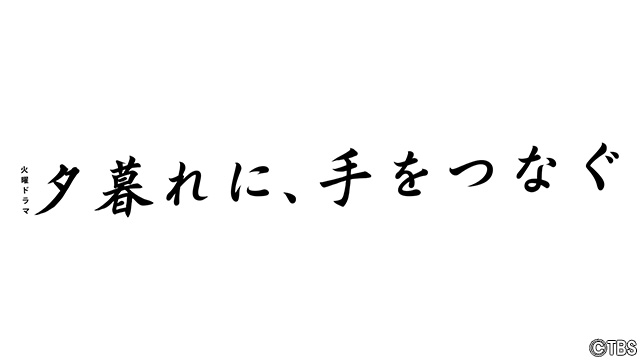やっと抱きしめ合えたのに、どうしてこんなに悲しいんだろう。
手を伸ばせば、いつも届く距離にいた。でも、手を伸ばすタイミングがちょっと遅すぎた。確かに腕の中に温もりを感じるのに、心はあの頃よりずっと遠く離れている。
『夕暮れに、手をつなぐ』(TBS系、毎週火曜22:00~)第9話は、浅葱空豆(広瀬すず)と海野音(永瀬廉)の終焉を描いた回となった。
美しく、切なくて、苦しい、別れの抱擁
何にも変わっていないはずなのに、何かが決定的に変わっている。そういうことは、人生の中で往々にしてある。「ちょっと早く着いちゃった」と空豆の壮行会にやってきた音は、一緒に住んでいたあの頃と同じ。縁側で並んでおしゃべりする時間も何も変わらない。だけど、何かが違う。
あんなに軽やかだった2人の掛け合いが、どこか弾まない。空気の抜けた風船みたいに、言葉がすべて地面に落ちていってしまう。季節外れの花火も、あの頃のシャボン玉みたいには無邪気にはしゃげない。こんなに近くにいるのに、すごく遠くにいるみたいだ。
「手をさ、伸ばしたら届く?」
空豆は聞いた。音は泣きそうになるのをこらえるみたいに「届くんじゃない? わりと簡単に」と空豆に歩み寄る。その言葉通り、空豆の伸ばした手は容易く音の頬に届く。
こんな簡単なことだった。こんななんでもないことが、できなかった。もっと早く素直になっていれば何かが変わったんだろうか。
かつて北川悦吏子は『Beautiful Life 〜ふたりでいた日々〜』で抱き合うと相手の顔が見えないということを言っていた。あのとき、本当にそうだなと思ったのを覚えている。
そして今、こうして抱き合う空豆と音を見て、相手の顔が見えないから、こんなに素直に気持ちを吐き出せているんだろうなと思った。遠慮がちな音が、空豆を強く、強く、抱きしめる。このまま自分の体に取り込んでしまえたらいいのにと、そんな声が聞こえるくらい、音は力強く空豆を抱きしめる。
その顔は、ぐしゃぐしゃだった。ずっと言えないままだった「好き」という気持ちが顔じゅうから溢れ出ていて、奔放な空豆に振り回さればっかりだった優しい音が、初めて聞き分けのない子どもみたいな顔をしていた。
もっと早くこんなふうに何もかもさらけ出せていたら、気持ちは届いたのだろうか。一緒に過ごす夏はあったのだろうか。いくら問うても時は戻らない。
「忘れんで」という小さく震えた空豆の声も、「忘れられっかよ」というやけに男っぽい音の返事も、どちらも2人の道がもう交わることがないことを前提にしているから、余計に辛い。
音の少し小さな肩に顔を預ける広瀬すずの涙は、結晶みたいに透き通っていて壊れやすくて。空豆の手の温もりを感じて、こみ上げてきたものを爆発させたように抱きしめた永瀬廉の表情は、抜けない針のように胸を貫いて苦しい。この2人だからこんなにも揺さぶられてしまうのだろう。思い出すだけで切ないのに、何度も反芻したくなるような、美しい別れの場面だった。
久遠徹に見る、北川悦吏子のものづくりへの情熱と畏怖
いよいよ『夕暮れに、手をつなぐ』も残すところ最終話のみとなった。このまま2人が離れ離れでエンドとなるのは正直あまりにも悲しすぎる。2人の青春の季節は終わってしまったのかもしれない。だけど、青春が過ぎても人生は続く。もう少し大人になった空豆と音が、もう一度、手をつなげる日が来ると信じたい。
そして、最終話の前だからこそ、改めて北川悦吏子の作品力について紙幅を割いてみたいと思う。今回、北川悦吏子のすごみを改めて感じたのが、久遠徹(遠藤憲一)の描写だ。天才デザイナーとして一時代を築きながら、自身の才能の枯渇にもがき苦しむ久遠は、どこか北川悦吏子のものをつくる人間としてのもがきと葛藤がそのまま投影されているように見えた。
新しいアイデアが出てこなくて、血反吐を吐くようにのたうち回る日々。同年代のクリエイターが一線を退いていく寂しさ。若い才能に対する嫉妬と畏れ。
久遠は長年愛用したソファを見ながら「経年劣化。カッコいいだろ?」と言った。もしかしたらこのドラマでいちばん好きな台詞はこれかもしれない。近年、物に使うはずだった「劣化」という言葉を人間に使う人が非常に増えた。美しい女優が年齢を重ね容姿に変化が訪れると「劣化」と侮蔑し、ちょっと陰りが見えたら「オワコン」と平気で人をコンテンツ扱いする。
北川悦吏子もまた近年、「時代に合っていない」と評されることが多かった。実際、いくつかの作品で僕も「時代に合っていない」と感じたのは事実だ。瞬く間にトレンドが移り変わる世界で、常に最先端でいることなど、きっと誰もできはしない。
でも、この『夕暮れに、手をつなぐ』には北川悦吏子の底力のようなものを強く感じた。あの2人が想像の世界で夢見た花火大会は、瀬名と南のスーパーボールのシーンのような、彼女にしか描けない独創性があったし、今回の送信取り消しによるすれ違いは「携帯電話の登場によってすれ違いが描けなくなった」と負け文句のように多くの人が恋愛ドラマにサジを投げる中、携帯電話があるからこそ生まれるすれ違いを、ちょっと悔しくなるくらい鮮やかに描いてみせた。北川悦吏子は、北川悦吏子にしか使えない魔法をまだちゃんと持っていると僕は思う。
そんな彼女が「経年劣化」という言葉をあえて台詞に入れたのは間違いなく意図的だと思うし、彼女のクリエイターとしての宣戦布告のようにも聞こえた。
久遠は「汚れ」をコンセプトに、己の新境地を切り開こうと動き出した。では、北川悦吏子はどんなふうにこれから新しい作品をつくっていくのだろう。
新品のソファのような真新しさはないかもしれない。もしかしたらデザインやシルエットはちょっと時代遅れかもしれない。でも、使えば使うほど味の出る革のソファのように、60代になった北川悦吏子が60代の北川悦吏子にしか書けないものをこれからも書き続けてくれたら、いちドラマファンとしてとてもうれしい。
もちろん毎回手放しで絶賛するつもりはない。でも、青春を振り返れば、いくつもの場面に北川悦吏子のドラマがあった。そんな世代の1人として、「今度の北川悦吏子ははたしてどうか」とドキドキしながら新作を観る。そして面白かったら「なんだかんだで北川悦吏子のイズムが自分の体に流れてるんだよな」と噛みしめる。それが、視聴者とつくり手の心地いい関係だと、『夕暮れに、手をつなぐ』を観ながら思った。